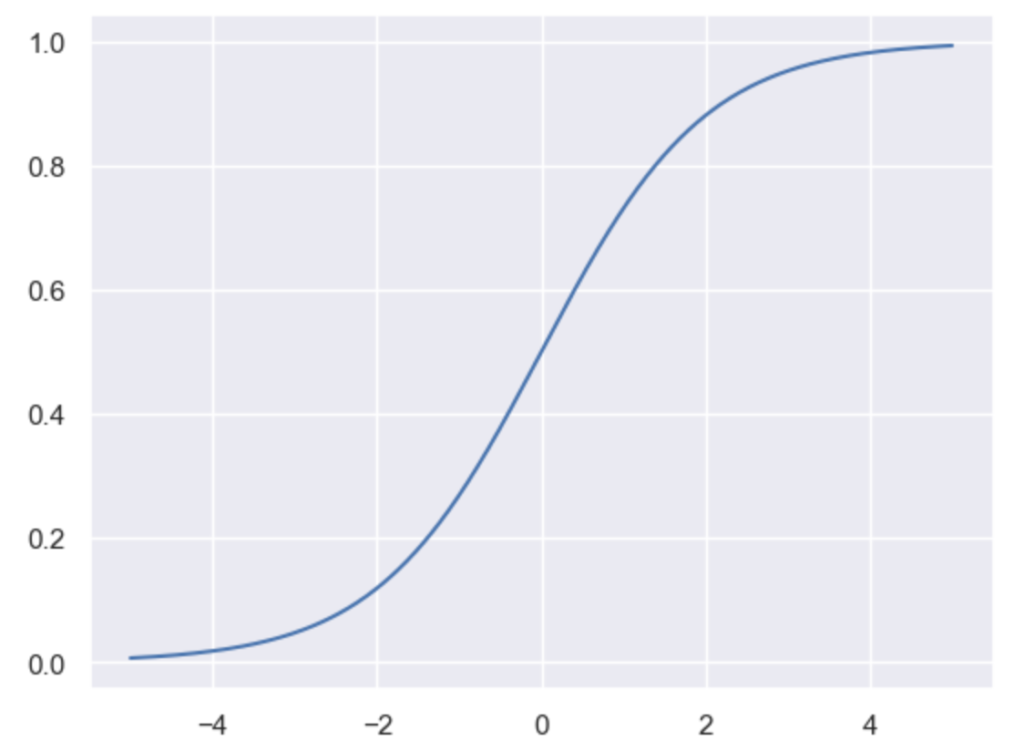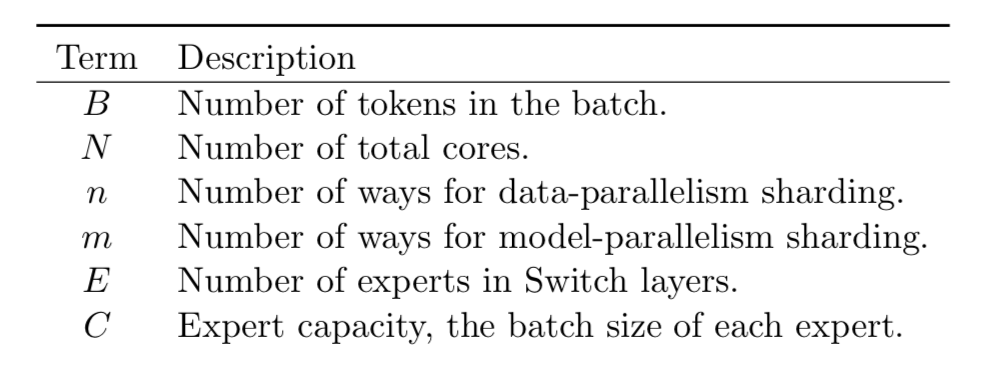「データサイエンス 数学ストラテジスト 上級」はデータサイエンスの基盤である、確率・統計、線形代数、微積分、機械学習、プログラミングなどを取り扱う資格試験です。当記事では「日本数学検定協会」作成の「公式問題集」の演習問題$31$〜$40$の解答例を取り扱いました。
・数学検定まとめhttps://www.hello-statisticians.com/math_certificate
演習問題 Q.31 $4$点が同じ平面上にあるとき、実数$s, t$について下記のような式が成立する。
$[1]$式の$1$行目と$2$行目より$s=1, t=-1$が得られ、$3$行目に代入すると$k=-2$が得られる。よって$(4)$が正しい。
Q.32 定積分$\displaystyle \int_{2}^{3} \log{(x-1)} dx$は部分積分に基づいて下記のように計算を行うことができる。
よって$(3)$が正しい。
Q.33 $f(x)=x^4-4x^3+10x^2+3x-1$とおくと、$f'(x), \, f^{”}(x)$は下記のように得られる。
$f^{”}(x)>0$であるので$f(x)$が下に凸の関数である。ここで$f(0)=-1<0$、$\displaystyle \lim_{x \to \pm \infty} f(x) = \infty$であるので$f(x)=0$は$2$個の実数解を持つ。よって$(3)$が正しい。
Q.34 $$
$[1]$式の両辺を$x$について微分すると下記が得られる。
ここで$\displaystyle y=f(x), f'(x)=\frac{dy}{dx}$とおくと下記が得られる。
上記に対し、$[1]$式に$x=0$を代入すると下記が得られる。
$[2]$式に$[3]$式を代入すると下記が得られる。
$[2]$式に$A=1$を代入することで下記が得られる。
よって$(3)$が正しい。
Q.35 $$
$f(x,y)$の$x$に関する偏微分を$f_{x}$、$y$に関する偏微分を$f_{y}$とおくと、それぞれ下記のように計算できる。
同様に$f_{xx}, f_{yy}$は下記のように計算できる。
よって$f_{xx}+f_{yy}$は下記のように得られる。
上記より$(3)$が正しい。
Q.36 $$
$\sin{x}$のマクローリン展開は下記のように行える。
上記より$(1)$式は下記のように変形できる。
$(2)$式が極限値$3$を持つので$\alpha=1$が得られる。また、$\alpha=1$を$(2)$式に代入すると下記が得られる。
よって$\displaystyle \alpha=1, \beta=\frac{1}{2}$より$6 \alpha \beta=3$であるので$(2)$が正しい。
・解説
Q.37 $$
以下、$f(x)$の$4$次導関数である$f^{(4)}(x)$を求める。
上記より$f^{(4)}(0)$は下記のように得られる。
ここで$f(x)$のマクローリン展開における$x^{4}$の係数は$\displaystyle \frac{f^{(4)}(0)}{4!}$であるので、係数は下記のように計算できる。
公式問題集の第$1$版第$1$刷の解答は日本数学検定協会公式の正誤表で訂正されていることに注意が必要である。
Q.38 $$
上記より行列$B$は下記のように得られる。
よって$(1)$が正しい。
Q.39 行列$\displaystyle \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$の逆行列は掃き出し法に基づいて下記のように得ることができる。
上記より逆行列は$\displaystyle \left( \begin{array}{ccc} -7 & -2 & 6 \\ 6 & 2 & -5 \\ -4 & -1 & 3 \end{array} \right)$であるので$(5)$が正しい。
・解説
Q.40 $$
上記が無限個の解を持つには「$\det{A}=0$が必要条件」となる。$\det{A}=0$は下記のように解くことができる。
ここで$\alpha=1$のとき解が定まらないので、無限個の解を持つのは$\alpha=-1$のときである。よって$(3)$が正しい。


![データサイエンス数学ストラテジスト[上級]公式問題集](https://m.media-amazon.com/images/I/51a6S+nLyWL._SL500_.jpg)